
DAY-2 午後の部

モデレーター
中島 信也(東北新社)小西 利行(POOL inc.)
宮田 人司(Mistletoe・OPENSAUCE)
午後の部は「新生EAT KANAZAWAどうすんの?会議」と銘打って、今回参加したゲストクリエイターを交えてのトークセッションが行われた。午前中に実施されたプレゼンテーションを受けての感想や、“EAT”となったEAT KANAZAWAは今後何をやっていくべきかなど、ゲストクリエイターそれぞれの思いが語られる場となった。
ゲストプレゼンテーション
●土佐 信道(明和電機)

トークセッションは、まず明和電機の土佐信道さんによる新作の楽器「SUSHI BEAT!」のデモで始まった。寿司を握るように本体を押すと音楽やリズムが流れ、IKA、TAMAGO、EBI、MAGUROの4種類のネタを握ってセッションできるという、まさにEAT KANAZAWAらしいガジェットだ。モデレーターの3人とのプレイで盛り上がった。
土佐:
食に関しては「鎖国食」がやってみたいですね。もしも今、日本が鎖国をしたら、ご飯はどうなるんだろうということに興味があるんです。例えば、大豆なんかは95%くらいが輸入に頼っているので、ミソとか醤油が手に入らない可能性が高い。すると、豆腐とお揚げのお味噌汁に、納豆に醤油をかけて食べようとしたら、全部大豆やん!という状況になってしまうわけです。自分たちの状況を見つめ直す機会になるのではないかと思ってます。
それと、昨日のディナーで感動したことがありました。料理はもちろん素晴らしかったんですけれど、気になったのはseccaの器ですね。テーブルの上に雪を降らせた「雪吊り」という料理の皿は紐で釣ってあったんですが、それがきれいにピンと張っていたんですよ。こういう工作をすると、普通は紐のどこかに緩みやゆがみが出るものなんです。すると、一本一本調整していたと聞いて、すごいこだわりを感じました。
●菱川 勢一(クリエイティブディレクター)

次にコメントしたのは、菱川勢一さんだ。午前中の話を聞いて、今の大学の若者に足りていない部分が気になったという。現在は高専(高等専門学校)の設立を進めており、教育、少子化といった課題の解決につなげたいと考えているという。
菱川:
僕は今、徳島県で高専の設立をしようとしているんです。高専は日本独自のシステムなのですが、民間での設立は実は54年ぶりの話なんです。もともと大学にも関わっているのですが、学生を見ているとけっこうメンタルをやられている子が多いんですよね。元をたどっていくと、高校のときに「これをやりなさい」という教育を徹底的にやられていて、それが目的を失っている原因になってるように思うんです。
そこで、高専という仕組みをうまく使って、独自の教育カリキュラムを作ってみたいと考えているんです。前期/後期や学期などを全廃するとか、飛び級できるとか、資格が取れるとか、夜のプログラムを作るなどですね。そのために全寮制にして、経済的に厳しい人は全額免除といったことも考えています。これらを実現するために、今、54年間変化のなかった高専の仕組みやルールを徹底的に洗い出して、認可が通るように戦っている最中です。
先ほど山本さんのお話に「サステナブルなエンターテインメント」という言葉が出てきましたが、教育にも同じようなことが言えます。日本は少子化が問題になっていますが、そもそも子どもが生まれたあと、自分の子どもは大丈夫なのかという不安を解消しないと、根本的に問題を解決することはできないと思います。そのための安心材料となる先行事例を作って、うまくいけばそれをひな形に全国に広げてもらいたいと考えています。
●孫 泰蔵
(Mistletoe・OPENSAUCE)

「教育といえば…」ということで、続いて指名されたのは孫 泰蔵さん。VIVITAという、子どもたちの好奇心を伸ばしていく新しいタイプのクリエイティブ・コミュニティーを起ち上げている。そこでの子どもたちの好奇心の強さには驚かされたという。
孫:
VIVITAという学校のプロジェクトを、千葉県柏市のの柏の葉、ハワイ、フィリピンなどで進めています。博多でもオープン予定で、さらにシンガポールやエストニアなど、その他の国々からもやってみたいという話が来ています。無料で、参加した子どもたちが作りたいものは何でも作らせるというスタンスなのですが、最初、子どもたちが作りたいものを思い付かない場合を想定して、好奇心を誘発するためのプログラムもたっぷり考えていました。でも実際は、そんなものは必要なかったんです。子どもたちはやって来るやいなや、あれも作りたい、これも作りたいと、好奇心の塊なんですね。一方、大学で学生たちと話をすると、「何をやっていいのかわからない」と言うわけです。これは、中学、高校時代に何かが起きているように思うんです。
昨日は素晴らしいディナーでしたが、アンドレシェフも髙木シェフも制約のない中で好きなことをやっていたと思いました。そして、クリエイターがやりたいことをやるという状況が、こんなにすごいクリエイションを生むということに度肝を抜かれました。現実的にはプロが関わるクリエイションには、従わなければならない制約や守らなければならないルールが常にあり、条件などを考慮しながらやることになります。でも、それが取り払われた世界はこんなに素晴らしいことになるのだということを、昨晩のディナーで見せつけられました。
今日お話をいただいた方々は、やりたいことを変に気負うことなく自然体でやってるのが印象的でした。遊びと学び、オンとオフ、そんな境目を感じさせない姿がとても自然に感じられたんです。
学習効率が最も高いのは「遊んでいるとき」という研究結果が出ています。でも実際は、勉強しようとして学ぶことが多いのが現状です。それは最も効率が悪い状態で、サイドブレーキを引きっぱなしの車で走っているようなものです。遊んでいるとき、人はサイドブレーキから解放されます。そうやって好きなことをやっているときが最も人が学べる時間なんです。EAT KANAZAWAは、そんな“思い切り遊べる場”であってほしいと思います。
●秋山 具義(アートディレクター)

グルメクリエイターとしても有名な秋山具義さんは、EAT KANAZAWAが食が軸となったことで「わかりやすくなった」という。グルメコミュニティの中で見つけた、子どもたちの好奇心を刺激するための提案があった。
秋山:
eATが“EAT”となって、食が含まれてきたことがうれしいですね。僕は何年か前から広告界で一番グルメな人だと思われようとして活動してきたんですけど、クリエイティブ業界での食のライバルが、平野紗季子さんなんです。彼女とはご飯を食べに行ったりするんですけど、話を聞いていると考え方がとても柔軟で、軽やかなステップで活動しているのが印象的です。それと僕はレモンサワーが大好きで、レモンサワーの連載記事を書いていたくらいなんですけど、田中 開くんはレモンサワーのライバルです。そのうちレモンサワーで何かやりたいと思っています。
先日、フレンチレストランの「カンテサンス」の岸田周三シェフと話す機会があったんですが、木村拓哉さんが主演のドラマ『グランメゾン東京』の監修をやってらして、料理の撮影などもすべて協力しているそうなんです。とてもたいへんらしいのですが、なぜ引き受けたかというと、料理の未来を考えたからなんですね。以前『ビューティフルライフ』というドラマで木村拓哉さんが美容師の役をやったのですが、ドラマが終わったあと美容師になりたいという若者がすごく増えたんだそうです。美容師に憧れた子たちがたくさんいて、結果、目指す人が増えたんですね。子どもたちにとって料理人がカッコいい存在になれるように、料理人が主役のドラマに協力したそうです。EAT KANAZAWAでは、子どもたちがいろいろな職業に憧れる場を作っていけるといいのではないかと思いました。
●原 雄司(3Dコンサルタント)

3Dの専門家であり、元格闘家でもあるという異色のクリエイター原 雄司さんは、お子さんが受験を終えられたばかり。自分の子どもの受験を通して、子どもたちがいかにして自分のやりたいことに出会うのか、考えたそうだ。
原:
うちの息子が受験で、一生懸命勉強をやってたんですけど、その理由のひとつが「行きたい学校があったから」なんですね。僕が3Dプリンターで子どもたちと遊んでいるシーンが学校のパンフレットに掲載されていて、それを見て、こんな楽しいことをやってる学校なら行きたいと思ったようなんです。「僕もお父さんみたいになりたい」とも言ってくれました(笑)。
将来何がやりたいのか聞いてみたんですけど、「ロボット博士になりたい」と言うんですね。僕は子どもをできるだけいろいろな研究者やクリエイターに会わせてあげたいと思ってるのですが、以前、ロボット研究家の石黒浩先生と会う機会があったんです。そのときに息子は、石黒先生といろいろと話をしたらしくて、相当影響を受けたようです。ただ、石黒先生はとても個性的な方なので「石黒先生みたいになりたい」と言われたときには、どうしようかと思ったんですが(笑)。
そんなふうに子どもがクリエイターに出会ったりすることで、その子の一生が変わりますよね。そういった機会を子どもに与えることは大切なのかなと思いました。われわれDiGITAL ARTISANでも、“DiGITAL ARTISANキッズ”をやってみようかという話もしているところです。
●REATMO(ヒューマンビートボックス奏者)

若者代表として意見を求められたREATMOさんには、「どうやってビートボックスにたどり着いたのか?」という質問が投げかけられた。今の自分につながっていく、少年時代の経験を語ってくれた。
REATMO:
教育に関連して思ったことですが、ここに来ているクリエイターの方々もそうだと思うんですけど、世の中には結構自由にやっている大人がいることとか、大人になってからも自分の好きなことを貫いている人がいるんだというモデルケースをどんどん発信して、子どもたちに見せていくことが大事だと思います。
僕は長野の田舎で育ったんですが、すごく閉鎖的な環境だったんです。しかも、もともと東京で暮らしていて、父親が実家を継ぐために戻ってきたという事情があったので、周囲が受け入れてくれなかったんです。しかも教育県だったこともあって、勉強はまじめに取り組まなければならず、とても窮屈でした。それでも小学生の頃は言われるままに過ごしていましたけど、高校生くらいになると自分がやりたいことも見つかるし、周囲との隔たりも大きくなってきて、どこのコミュニティにも所属していない自分は外に居場所がないことに気が付いたんですね。そうなったとき、自分の好きなこと、僕の場合はビートボックスや音楽ですけど、それに夢中になって自分で自分の居場所を作る必要があったんです。それが今の僕につながっていると思います。僕はひとりでテレビや音楽などのエンターテインメントを見ていて、それにすごく救われました。だからエンタメに興味を持ったし、自分を救ってくれたエンターテインメント自体になりたいという気持ちもありましたね。
僕はマルーン5が大好きで、今は交流もあるんですが、初めて会ったときに彼らのことを観察してみたんですよ。あれだけのビックネームなのに本当に気さくな人たちだったんですけど、ひとつだけ普通の大人と違っていたのが、好奇心がものすごく強いことなんです。日本を案内していてもすぐにどこかに行っちゃうような感じで、その好奇心の強さが彼らの成功に結び付いたんじゃないかなと思いました。
●北川 力(WOTA)
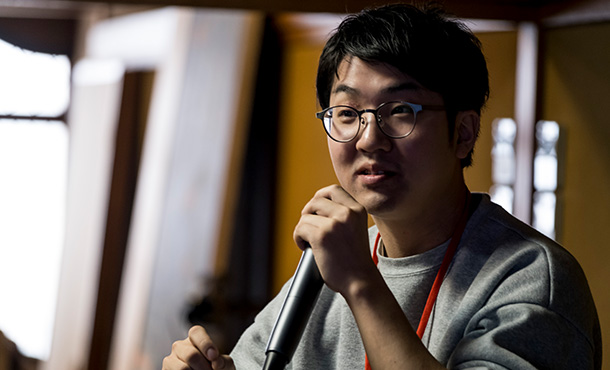
使用済みの水の浄化と再利用など、世界中で起こっている水資源の問題を解決しようと、水についてのさまざまな研究を進める「WOTA(ウォータ)」。代表である北川 力さんには、「なぜ水に夢中になったのか?」という好奇心の源泉についての質問が飛んだ。
北川:
僕が水に興味を持ったきっかけは、どこに行っても、何をやっていても、水については世界共通でつながることができるというのがひとつ。それと僕には恩師がいて、先生にはよく「何をやればいいのか」という相談をしていたんですが、いつも「とにかく好きなことをやればいい」と背中を押してくれていたんです。そうやって僕の知的好奇心の広がりを妨げないようにしてくれたおかげで、自分でどんどん掘り下げて研究することができたんだと思います。簡単に言えば、ワクワクするから続けてられる、ということですね。
実際に水の世界に入ってみると、とにかく奥が深いんです。例えば、水はいろいろな文化のベースになっています。食と水の関係などわかりやすいと思うのですが、水とアートの関係というのもあって、日本や中国は軟水なので水彩画や水墨画の文化が発展しましたが、硬水のヨーロッパではうまく墨が扱えないので繊細な表現ができず、だから油絵のどぎつい表現になっていたという話もあります。地域の文化など、さまざまなものを理解していく上でも、ベースにあるのは水なんです。だから、水は面白いんです。
●加藤 拓(演出家)
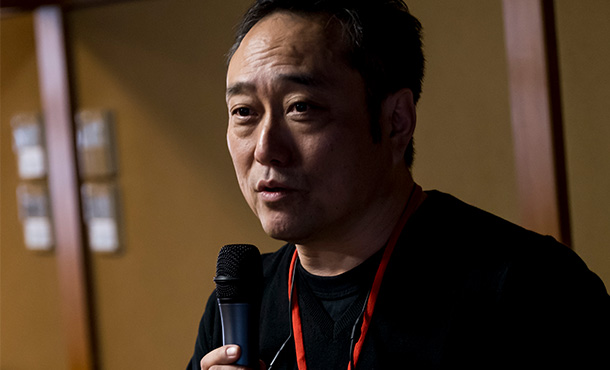
「枠組みや条件の中でほうが仕事がしやすい」という加藤 拓さん。中国での撮影で、その枠組みをぶち破るような若者の仕事を見てきたという。しかしそのムーブメントは、日本でも静かに起きていることを感じたそうだ。
加藤:
僕はテレビドラマを作ってきたんですが、最近は、現場を若者に譲ってハンコをつく仕事に回るようにしています(笑)。でも、そうやって若い人に役目を与えてみて、その仕事ぶりを見ていると、みんなものすごく優秀なんです。
先日、8Kの映像を中国で撮るということをやってみたくて挑戦しました。そのとき僕らは20人の体制で中国に向かったんですが、着いてみると200人という大量の現地スタッフが待ち構えていたんですね(笑)。そしてその仕事ぶりには圧倒的なパワーがありました。200人の中に30人ほどの「場巧(じょうこう)さん」がいました。レールは敷く、水は運ぶ、弁当は配る、スモークを焚く、と何でもやる人たちなんですけど、その場巧さんを仕切っているのが、劉くんという若干19歳の若者だったんです。劉くんはもちろん若いわけですけど、現場をとにかくパワフルに仕切っていくんです。その勢いがすごいんです。中国で8Kでドラマ撮影というと最先端で大きなプロジェクトだし、これを通して若いスタッフに自信を持ってもらって、さまさまなフィードバックを得てもらおうと思っていたんです。でも、現地のパワフルさに逆に打ちのめされることになってしまいました。
彼らのパワーの源泉は何かというと、現在の中国の右肩上がりの産業の勢いやプライドにあるように思うんです。日本では、自分たちの手の中に収まるサイズの豊かさを大切にしようという考えがありますが、それをまったく別の方向からぶち破っていくような、そんなインパクトがありました。
でも今日、若い人たちのお話を聞いていると、既存の枠組みを突き破っていくような人たちが日本からもたくさん出てきているんだなという感想を持ちました。
●山口 裕美(アートプロデューサー)

山口 裕美さんは今年、明治神宮の創建100周年を記念して展覧会を神宮内で開催する。明治神宮に現代アートが展示されるという初の試みに挑戦している山口さんは、午前中のプレゼンに自分も同じ状況だと共感していた。
山口:
今日のお話を聞いていていくつか思うことがあったのですが、ひとつは「好きなことを仕事にできているというのは、相当運がいい人なんじゃないか」ということですね。皆さんは好きなことを仕事にできた人だと思うのですが、私も好きなことを仕事にしてきました。私はアーティストを応援するのが好きなんです。才能があってお金がない、やる気があってチャンスがない、そんな人たちを応援して、例えばEAT KANAZAWAに連れてくるのが私の役目だと思ってます。
それと「努力は情熱にかなわない」というある方の言葉があるのですが、例えばトンコハウスの話を伺っていても、やはり情熱が努力に勝ってるよ、と思うわけです。
私自身の話をすると、私は美術大を出ているわけではないし、もともと観る側の人間ですが、アートが病的に好きだったので、業界のことは知っています。アートの世界というのはとても狭くて保守的です。世界の最先端であるはずのアートがすごく狭くて、保守的で、どうしようもない状況なんです。才能があっても、東京芸大を首席で卒業しても食べていけない──おかしいじゃないか! ということで、私はアートを好きなったのは“病気”で、そこに注ぎ込む情熱は“怒り”なんですね。病気と怒りを両輪にして、がむしゃらにやってきました。
今日、お話を聞かせてくれたみなさん、素晴らしい内容だったんですけど、私個人はあまり世代間のギャップを感じませんでした。私は今年、明治神宮の創建100周年を記念した展覧会をプロデュースしました。現代アートが明治神宮に初めて展示されます。自分の好きなことを追究した結果、新しいことに挑戦している皆さんですが、私も今、同じことに直面しているように感じています。
●林 信行(ジャーナリスト)

もともとテクノロジーを追いかけていたが、最近はアートを追っているというジャーナリストの林 信行さんが、その変遷について話してくれた。そこには、自分のモチベーションが向く方向に躊躇なく進んでいくというスタイルがあった。
林:
僕も教育に関わっていたことがありました。大学のカリキュラム作りを手伝っていて、アドバイスしながら長い時間をかけて話し合ってきたんです。今の学生がやりたいことにフォーカスして新しいカリキュラムを作ろうという話になり、面白いアイデアもたくさん出て、講師たちのテンションも高くて、うまくまとめればいいものに仕上がるというところまで来たんですね。でも実際のシラバスに落とした物を見せてもらったら、あんなに時間をかけて考えてきたのに、まったく興味が湧かない内容になってしまっていたんです。何かが新しいカリキュラム制作の障害となったわけです。学生のモチベーションを高めることが大事だということにはみんな気が付いているにもかかわらず、実際にそのためのアクションを取ろうとすると、戦わなければならない何かが社会には存在するということを、あらためて思い知りました。
モチベーションを高めるために何をするかということなんですが、やはり興味が向く方向に進んでいくことだと思います。例えば僕の場合、よくテクノロジー系のジャーナリストと言われますが、自分が本当に興味があるのはテクノロジーではなくて、未来を創ることや未来を創るものだったと気が付いたんですね。小さい頃はテクノロジーが未来を創っていると思っていたんですが、最近はテクノロジー自体は良い未来を創っていないように感じています。例えば、世の中を変えることになったAppleのiPodは、発売された当時、テクノロジー的に新しい仕組みは何も搭載していなくて、スティーブ・ジョブズの「ポケットの中に1000曲入れて持ち歩きたい」というコンセプトと、それを実現したプロダクトデザインが素晴らしかったと思うんです。未来を創るのはテクノロジーではなくデザインじゃないかと思い、しばらくデザインを追いかけました。
最近は、またそれも変わってきました。スマートフォンは世の中を変えましたが、スマートフォン以上に世の中を変えるものが登場するとき、その先の未来を創るのはアートや哲学じゃないかと考えています。だからSNSを通して、世間にアートの素晴らしさを伝えるように投稿したりしています。そんなふうに、自分の興味、モチベーションを追いかけながら、世の中を攪拌していくことが、自分の役目なんじゃないかと思っています。
●菊川 裕也(No new folk studio)

「スマートフォン以降」という話が出たが、スマートシューズというジャンルで、まさにスマートフォン以降を体現する仕組みを開発している菊川裕也さんに声がかかった。“人をわかってあげる”デバイスについて、説明してくれた。
菊川:
僕は、履いて走るだけで、走り方を計測して教えてくれるといった機能を持ったシューズを開発しています。靴がスマートになってインターネットにつながる面白さというのは、人間が意識していない動作がネットにつながることだと思っています。「足取り」という言葉がありますけど、疲労などによって人の歩き方は一日の中で変わっていってます。また、「歩容」という言葉がありますが、歩き方というのは「歩容認証」という技術があるくらい、個別のユニークなステータスなんです。僕らがやろうとしているのは、そのひとりひとりの歩容のデータをすべてネットに保存してあげて、その人がいつまで健康的に歩くことができるのか観察するとか、この人はトイレに行きたいようだから場所を教えてあげるとか、人のコンテクストを読み取ってあげるコンピューティングのようなものを実現することです。それはまさに「スマートフォンの次」という存在を目指しています。
今興味あるのは、音楽で人を変えるということです。好きな音楽を聴きながら走ると、人は「無酸素作業域値」が10~20パーセントのレベルで向上することがわかっています。聴いてる音楽によって動きがよくなるわけです。履いている人の状態をリアルタイムでわかってあげることができれば、その状態に対して音楽でフィードバックするという仕組みが作れないかと考えています。「この音楽を聴きながら走れば疲れない」とか「ケガをしにくい」といった具合ですね。
今日のみなさんのお話を聞いていて、基本的に学ぶべきは大人なんじゃないかと思いました。子どもには希望があるし、今回の若い方々の話も希望に満ちあふれていましたよね。むしろ聞いている大人のほうがヤバいと(笑)。なので、EATには大人が勉強できる場を提供してもらえればいいなと思いました。
●山本 雅也(KitchHike)

最後は、やはり食に関わるプロジェクトを進めている、KitchHike(キッチハイク)の山本雅也さん。世界中の家庭の晩ご飯を食べ歩いた結果、食の持つポテンシャルをストレートに体現する「みんなでご飯を食べる」というプロジェクトに至った。
山本:
いろいろな世代間の話も出ましたが、ジェネレーションごとに空気感を作っている職業は何だろうと考えたとき、60~70年代はミュージシャン、80~90年代は建築家が、90~00年代は広告が、2010年代になって明らかに食に関わる人たちが作っていると、あらためて感じました。
われわれキッチハイクがやっているのは「みんなでご飯を食べよう」というシンプルなことです。会社員をやっていたある日、つながるための食のあり方があるんじゃないかということを思い付いて、会社を突然辞めて、世界中の人とご飯を食べ歩くということをやってみたんです。1年半くらいかけて約50カ国を回り、人の家に入れてもらっていっしょにご飯を食べるということを70回ほどやりました。実際にやってみてわかったのは、人のうちでご飯を食べるという行動には世の中を変えてしまうほどのインパクトがあるということです。世界中のどの家庭でも、いっしょに手料理を食べさせてもらうと、一瞬にして仲良くなれるんですね。これを世界中の人がやったらものすごいことになるぞと思って、キッチハイクを始めました。
キッチハイクは、人の家のご飯を食べて仲良くなるということから始まりました。今は、お店でみんなでご飯を食べるというところまで拡張しています。その背景として、素人料理人のプロ化というものがあります。友達にご飯を作っていたら話題になって、いつの間にか有名になっていた方もいます。その一方で、お店で食べる料理で一番贅沢なものって、僕はプロの料理人が作る賄い料理だと思っています。家飯が外食化する、外食が家飯化するという現象があって、その辺りがかけ合わさったところに、2020年代の食のあり方が存在するんじゃないかなと考えています。
●小西 利行(POOL inc.)

一般参加者からの質問や感想を聞いたあと、最後に、今回のディレクター役を務めたコピーライターの小西利行さんが、新しいEAT KANAZAWAのステートメントをまとめた。今日のセッションを含む2日間のイベントを体感して、そこで得たものをこの場でコピーに落とし込むという、ライブコピーライティングとも呼ぶべきパフォーマンスとなった。
小西:
こういったセミナースタイルの場ですから、みんなから知恵の実を与えてもらうという印象があります。でも、今回のキーワードは「好奇心」だと感じて、受け取ったのは知恵ではなく好奇心の実なんじゃないかと思うんです。誰かから一方的に知恵だけを与えられるのではなく、「すごい!」「面白い!」「それやってみたい!」という好奇心を育む実を与えてもらって、受け取った人が反応していく場だと感じました。さらに、みなさんのお話に出てきたたくさんのキーワード、話題に上ったテーマを織り込みました。そして何と言っても“EAT”になったわけですから、やはり食べることを中心に置きたい。
そうして考えたのが、この言葉です。
![]()
さあ、知恵の実を集めよう。情熱の実を味わおう。
遊びの実を手に入れよう。
いろんな好奇心を、いろんな世代でシェアして、
肩の力を抜いて、遊ぼう。学ぼう。笑おう。
そして、金沢から日本へ、新しい憧れをつくっていこう。
あとがき
こうして新しいEAT KANAZAWAスタートへの準備が整った。どういう場になるのか、何が起きるのか、毎回わからないところがこのイベントの特徴であり、良さだった。ただ今回は、いったん休止のあとの再出発とあって、始まる前には実行委員にも参加者にも、うっすらとした緊張感が漂っていたように感じた。しかし、初日の究極的にクリエイティブなディナーによる“EAT”体験で全身を揺さぶられ、ゲストクリエイターを含む参加者は、eATからEATとなることを選んだこのイベントに大きな可能性があるということを確信できたように思う。翌日のトークセッションのラインナップと盛り上がりも、それを裏打ちするものだった。
金沢にはさまざまなイメージがあるが、クリエイティブな好奇心を刺激する街というイメージは確実に根付いている。それを20年以上にわたって力強く支えてきたEAT KANAZAWAが、来年から正式に帰ってくる。